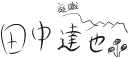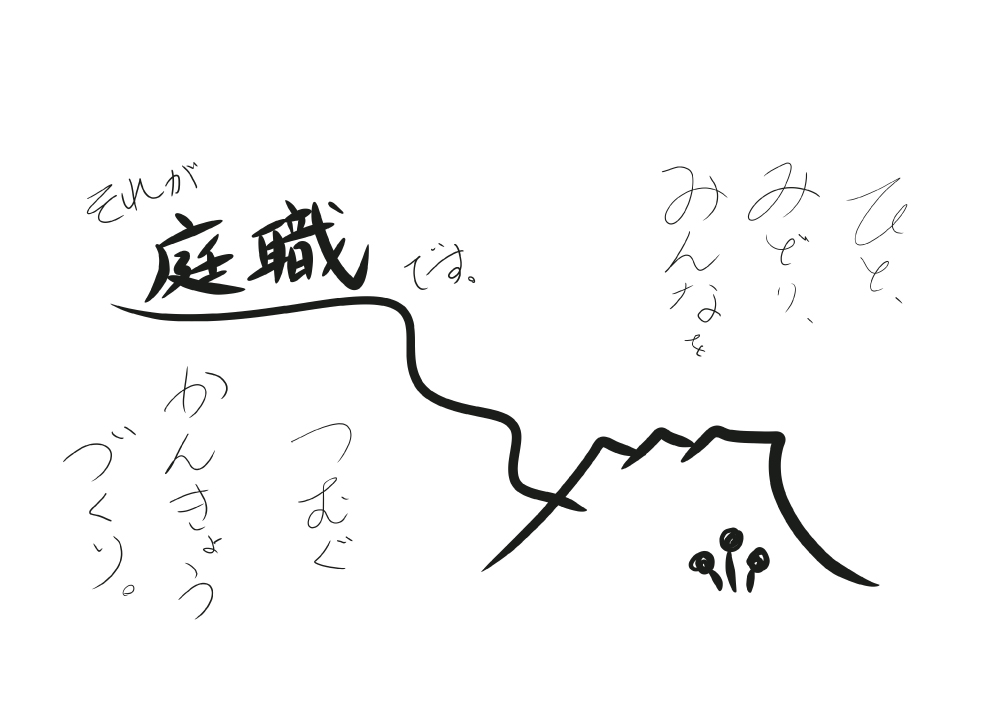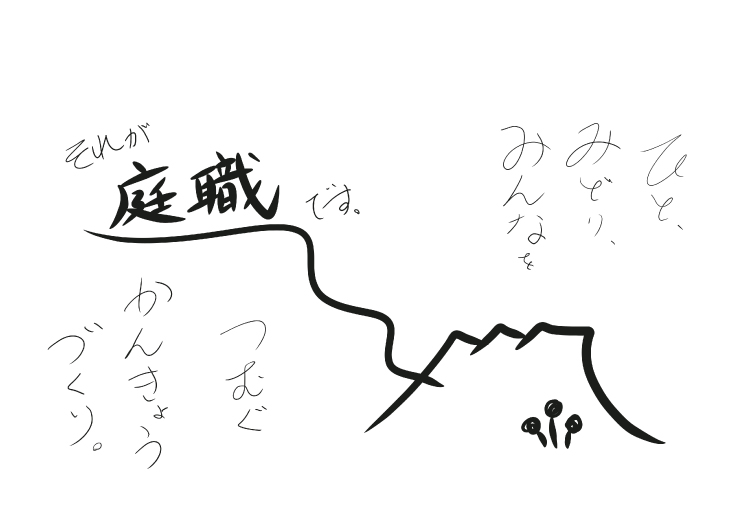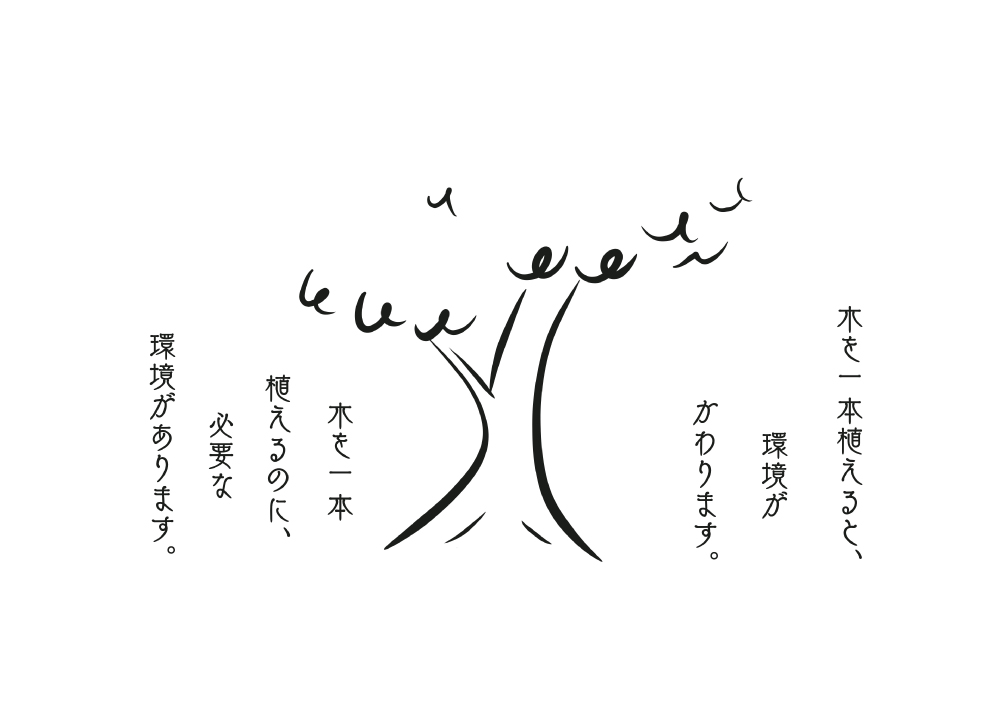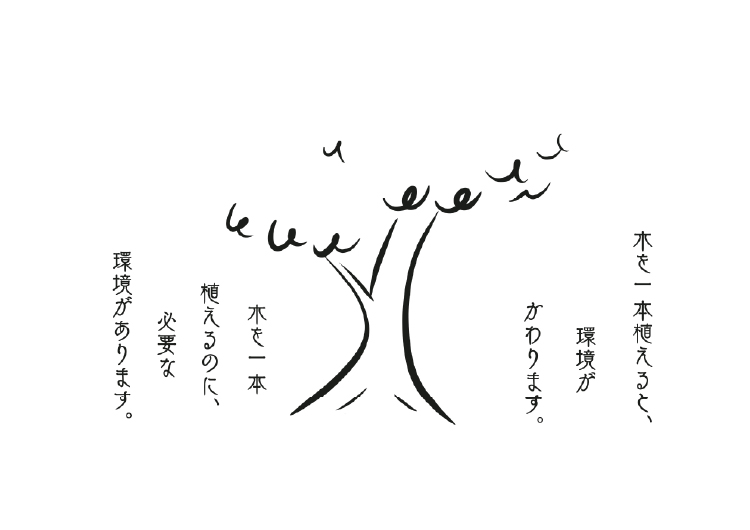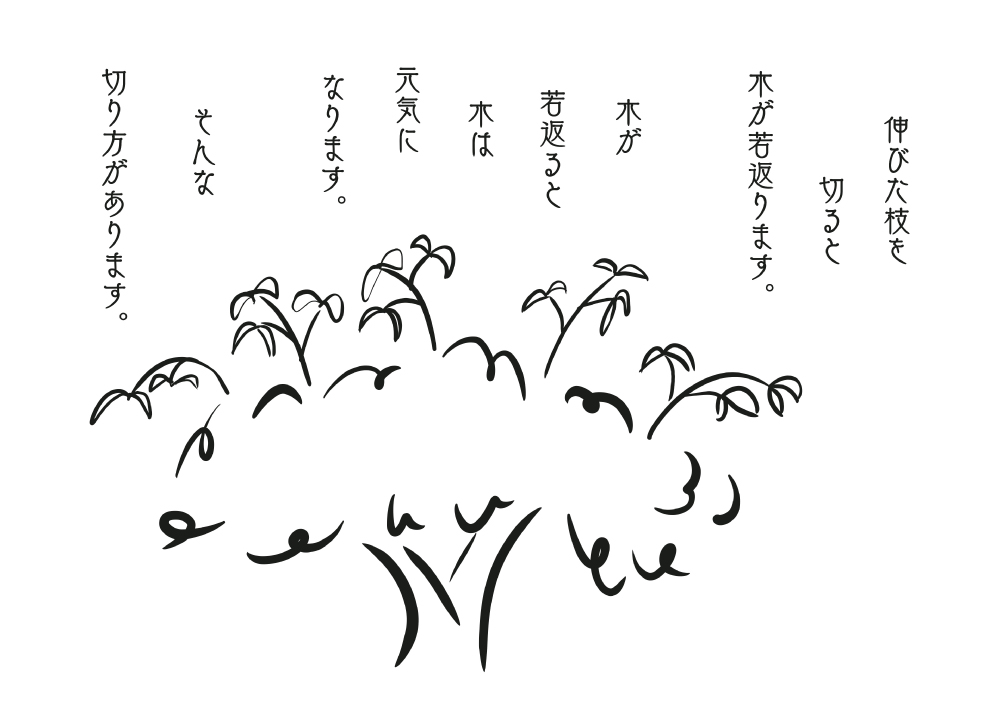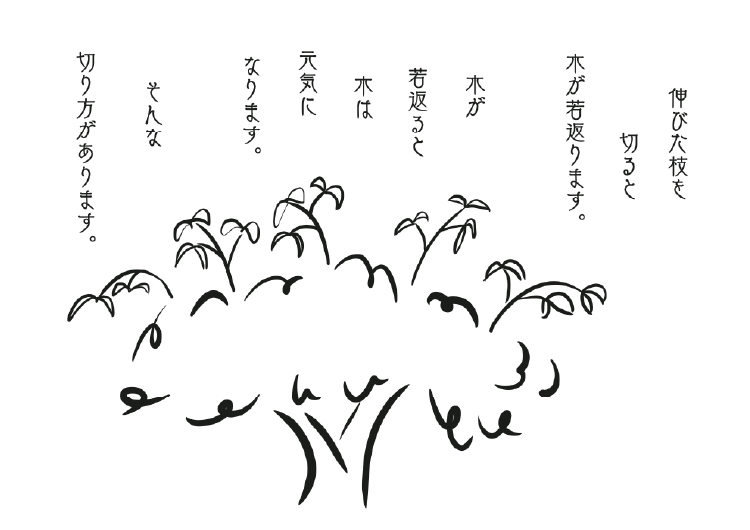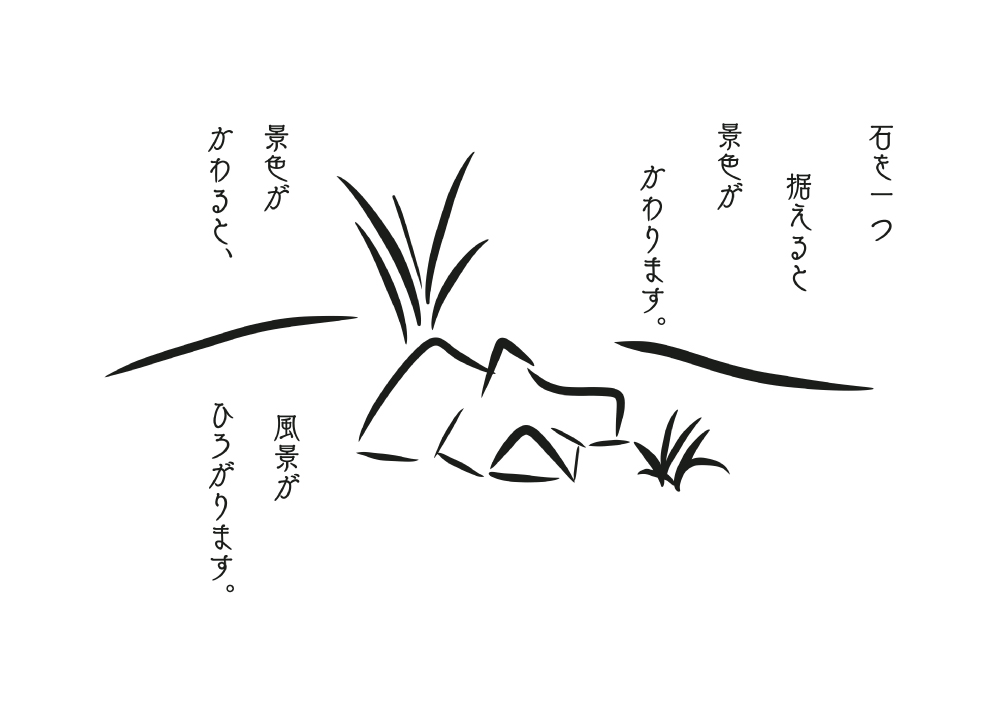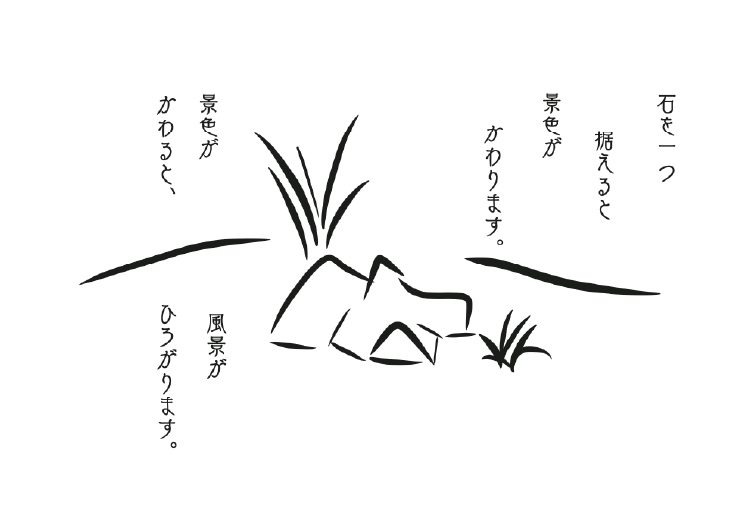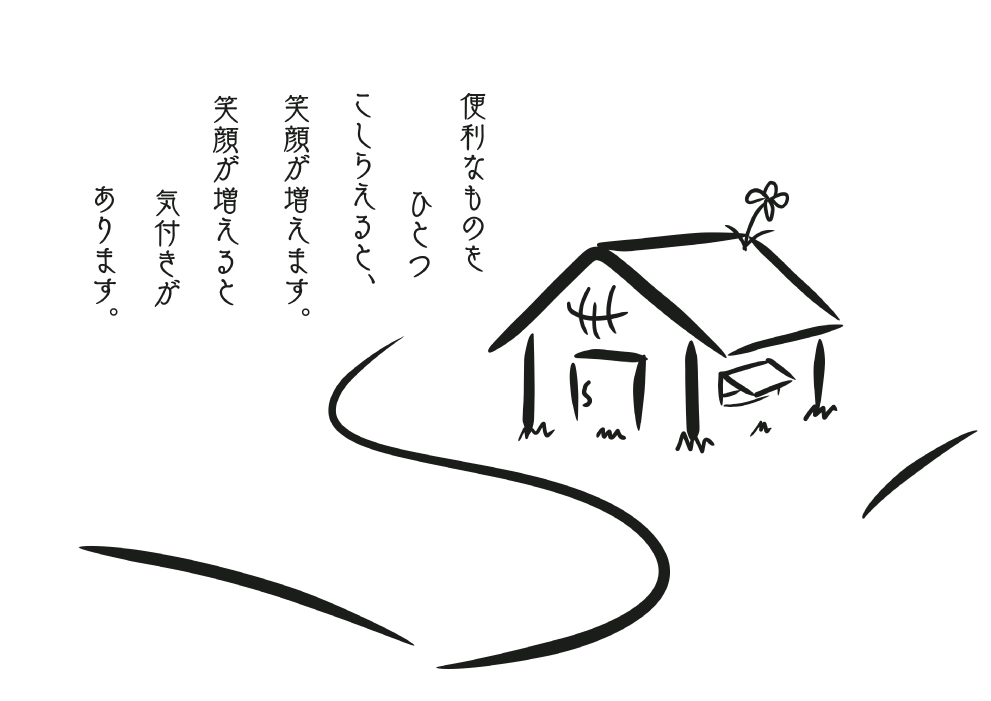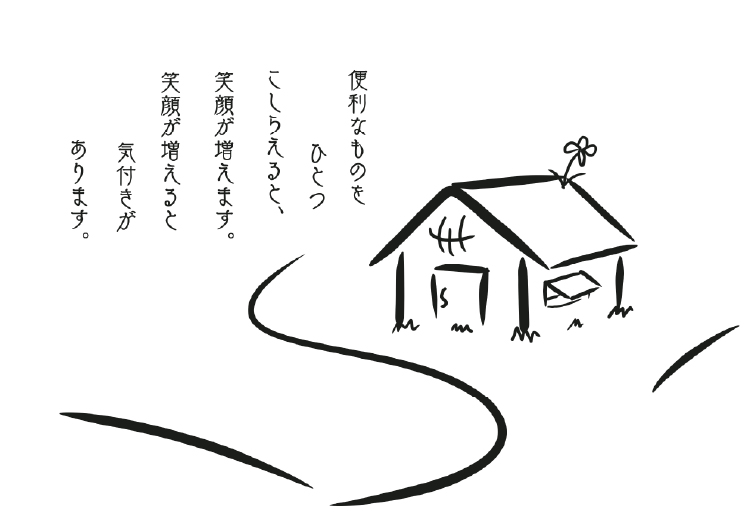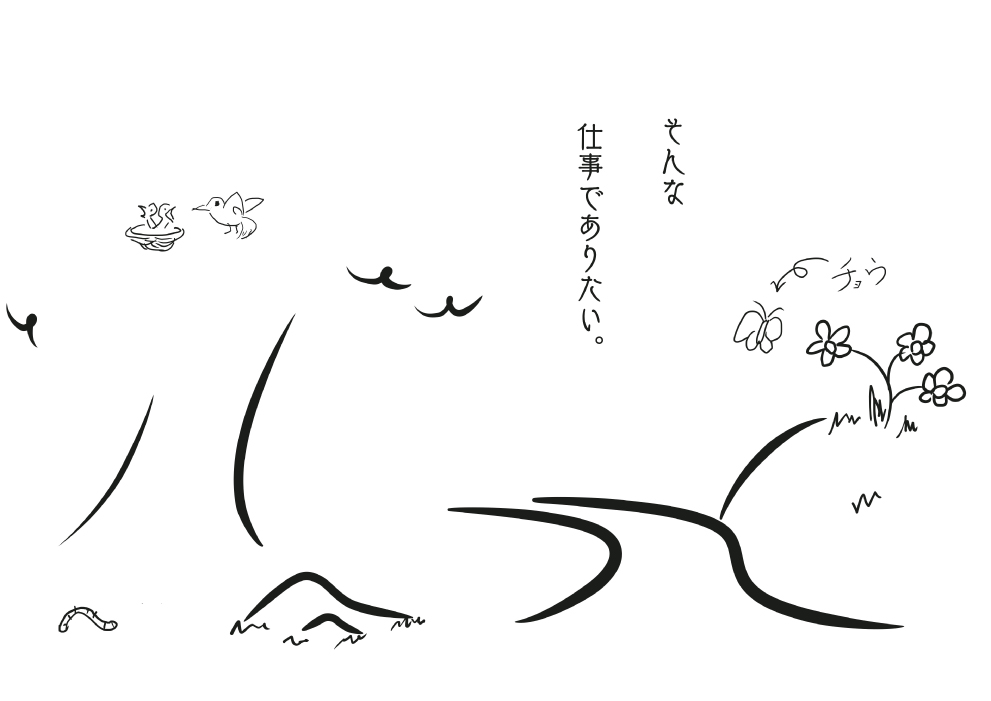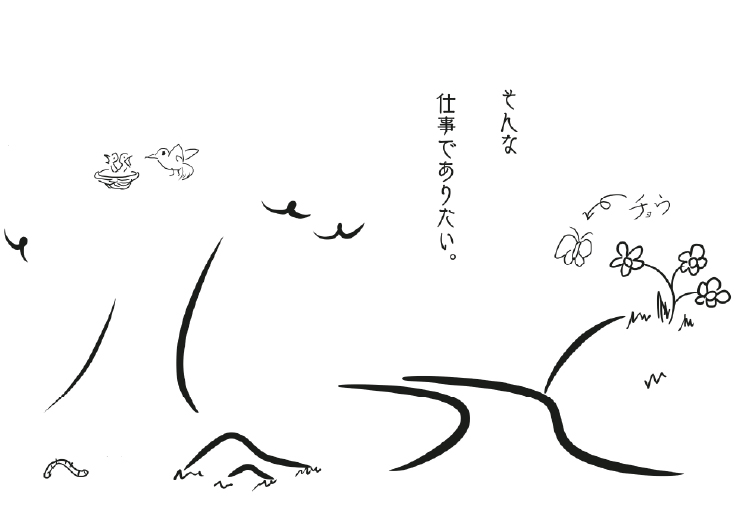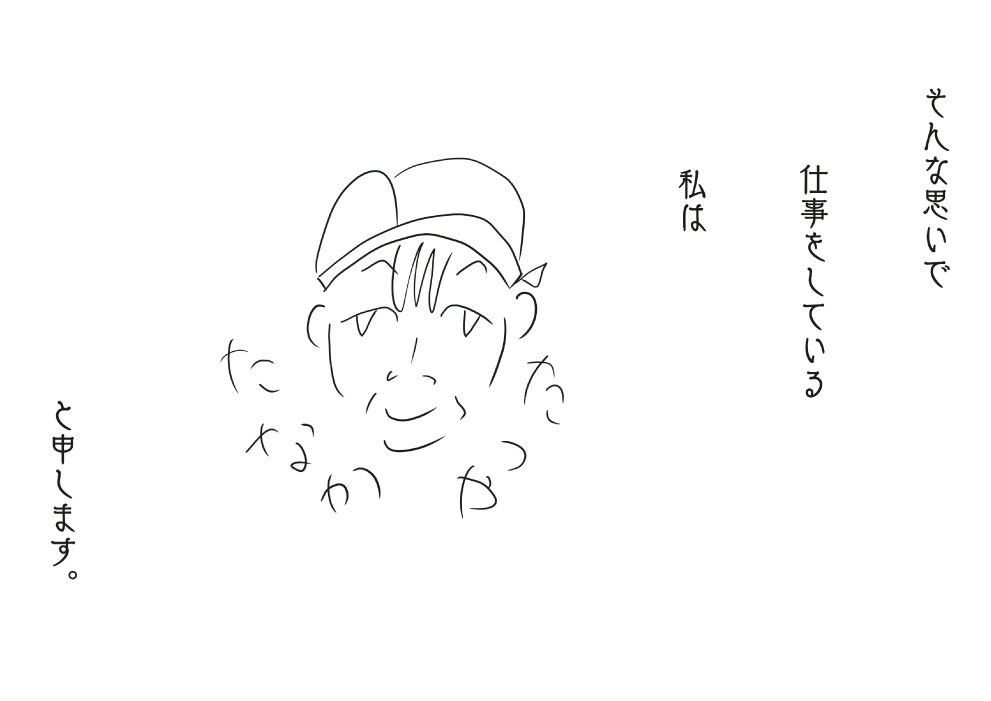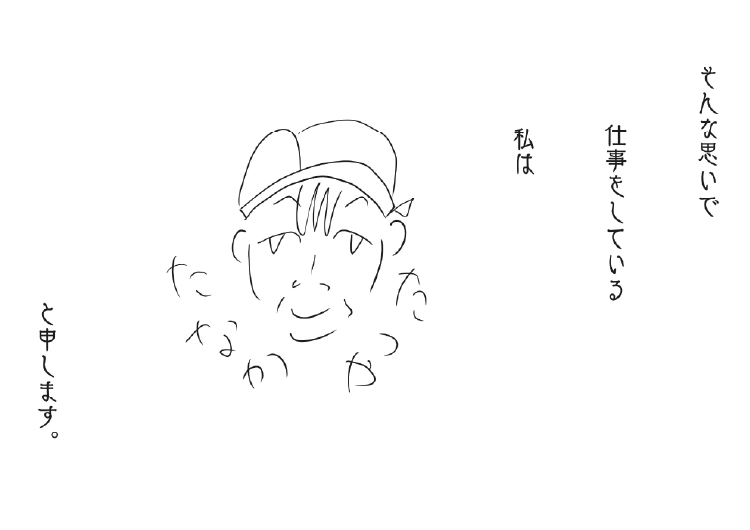全てのカテゴリ
-

- あるものリガーデン
- 芝のメンテナンスからの解放を望まれるお施主様から、美観も含めたリガーデンのご依頼を承りました。<div>その際に経済面や無駄をなくす観点からご自宅で余っているレンガやガーデンファニチャーを使えれば使ってほしいとのご要望もありました。</div><div><br></div><div>そこで諸々のご要望にお応えできる手段として、芝生から土系舗装への変換とレンガによる装飾、レンガとアイアンのガーデンファニチャーを用いた飛び石による装飾と動線の誘導でした。</div><div>円形の飛び石は施工個所にあった雨水枡の存在感を薄めるうえでも有効に働くと思いました。</div><div><br></div><div>現状合わせでの水勾配や飛石表面の排水性には苦心したもののご容認いただけるものを完成させる事が出来ました。</div>
-

- 園路の石張り
- こちらのお庭はアトリエブロンズリーフさんがリガーデンを手掛けるお庭で、その一環として園路の施工を行いました。<div><br></div><div>要ともなる園路ですので、幅や曲がり具合など、綿密に確認しつつ決定したら、いざ石張りです。</div><div><br></div><div>大、中、小のバランスや形状を見極め配置を大まかに決めたら次に石の加工に入ります。</div><div>もともとその形であったかのように加工するのが大切になります。</div><div>そうして全体の配置が完全なものとなったら、いったん石を外し下地をつくり再度石を置き目地を入れていきます。</div><div>最後に余分なモルタルを拭き取って完成です。</div><div><br></div><div>お施主様にも大変気に入っていただけました。</div>
-

- 木の温もりを感じる庭
- こちらのお宅では、ウッドフェンスから始まり外水栓まわりのリフォームや縁台の取り換えをさせていただきました。<div><br></div><div>ウッドフェンスでは浮づくりの杉板を使用し、日本的な雰囲気を出しつつ縦づかいにする事で牧歌的な印象を与え、のどかさを演出しました。</div><div>続く外水栓まわりのリフォームも、ウッドフェンスと連続性を持たせるように手を加えていき、改善の対象である素材からくる殺風景さや装飾性のなさ、棚に置かれた物が目につく事で感じる乱雑さを解消させました。</div><div><br></div><div>最後の作業となる縁台の交換では、夏の日差しでアルミ製の座面が熱くなるため木製のものにしたいという事で、設計から施工までをさせていただきました。</div><div>今回の設計では、まず最初に細い垂木を細かく並べた座面のイメージがあり、それを支える躯体を角材ではなく板材で組んだら面白いデザインになるんじゃないかという期待のもと設計施工させていただき、イメージ通りのものが完成したと思っています。</div><div>しかもこの縁台の座り心地のよさは思いのほかで大変うれしかったです。</div><div><br></div><div>けれど何よりも、今回の一連のリフォーム工事を通して、私の考えや着想を尊重していただき、またそれを気に入っていただけた事が一番の喜びでした。</div><div><br></div>
-

- スダジイ
- <strong>スダジイ</strong><div>〇ブナ科シイ属 / 常緑高木 / 雌雄同株 / 日当たりのよい所を好む</div><div><br></div><div>照葉樹林を形成する代表的な樹木のひとつで神社の境内や鎮守の森でもよく見かけるスダジイは、一般的にはシイノキと呼ばれ庭木や公園樹木としてもよく見かける。若葉の頃に黄金色の花序で樹冠を飾り独特の芳香を放ち虫を誘う、人にとってはいい香りというよりはむせるような香りである。実りの秋にはたくさんのどんぐりがなり森の生き物の貴重な食料となる。人にとっては自然工作の材料としての方が馴染み深いが、スダジイのどんぐりはカシやコナラなどの他の種のような渋みはなく、甘みがあり食べられる。</div><div><br></div><div>スダジイの近縁種にはコジイがあり、別名ツブラジイとも呼ばれ、二種の見分けは難しい。大きな違いとしてはスダジイの幹では縦に割れ目ができるがコジイは平滑で割れ目ができない事や、スダジイのどんぐりが長楕円形なのに対しコジイのは球形になるという違いがあるほか、環境と分布地の違いではコジイは乾燥地を好み、スダジイは海沿いや河川流域、山地の斜面地などの空中湿度の高い土地を好む。スダジイの分布は福島県以南で日本海側にも新潟県佐渡島を北限に分布があるがコジイは関東以西の内陸部を中心とし日本海側にはほとんど分布がない。</div><div><br></div><div>また、スダジイは長寿の樹木で照葉樹林を形成するのに対しコジイは腐朽菌が入って枯死しやすいため照葉樹林ではスダジイにとってかわられる。照葉樹林とは極相林ともいい、いわば森の完成形で、言い換えれば人の手が加えられていない森という事なので、そういう森は全国的にもほとんど残っておらず、スダジイの大木も数は少ないとされてきたが近年、伊豆諸島にはスダジイの大木が比較的多く残っているらしい。</div><div><br></div><div>シイ類に入りやすい腐朽菌はシイサルノコシカケで公園樹木や庭木でも度々目にするが、シイサルノコシカケがあるからといって即座に伐採が必要かといえばそうではなく、枯れたり倒木の危険があるかの判断は慎重に行う必要がある。</div><div>また、庭木でシイサルノコシカケに侵されるのには剪定が多少なりとも影響している場合がある。というのも関東では以前まで敷地の境界にシイノキを植えていたという。以前に比べ越境枝に神経を使う近年の住宅事情ではその事でかえって強剪定の対象になりやすいからだ。</div><div><br></div><div>スダジイの大木が少ない理由には木材としてあまり有用ではないという事も影響している。木材として使われなかったため、植林もされず森林開拓で減るばかりだった。木材以外の利用用途としては、シイタケの原木や樹皮を乾燥させて染料として使われてきた。</div><div><br></div><div>〇スダジイの手入れ</div><div><br></div><div> 剪定 2~6月 及び 9月~11月</div><div><br></div><div> 移植、植栽 2月~3月 及び 5月~6月 </div>
-

- アカマツ(赤松)
- <strong>アカマツ(赤松)</strong><div>○マツ科マツ属 / 常緑高木 / 雌雄同株 / 日当たりの良い場所を好む</div><div><br></div><div>アカマツは、その赤みがかった幹の色からそう呼ばれます。</div><div>同じく幹の色からの呼び名のクロマツと比べると、葉は少し短く柔らかく、色味も鮮やかな緑で見た目にもたおやかな雰囲気を伺わせます。庭木に仕立てられるとその印象は顕著で、そのため雄々しいクロマツを雄松(オマツ)、男松(オトコマツ)アカマツを雌松(メマツ)、女松(オンナマツ)と呼びます。</div><div><br></div><div>この二者は生育環境も共に共通してやせ地で乾燥地を好みますが、クロマツが平地や海岸に多いのに対し、アカマツは尾根や岩場に多く、時に他の樹木が育たない湿地にも生育します。</div><div>貧栄養の土壌を好むのは先駆植物の特徴とされますが、実はこの特徴と人とマツとの関わり方が全国の松原の衰退を招く一因となっている現状があるようです。</div><div><br></div><div>静岡の「三保の松原」と佐賀の「虹の松原」と共に日本三大松原に数えられる福井の「気比の松原」はアカマツが六割近くある全国でも珍しいアカマツの多い松原ですが、その規模は衰退をたどり、戦前と戦後ではその面積は半減しており、その要因は松原の利用の変化によるところが大きいようです。</div><div><br></div><div>ここでマツの人による利用について触れると、松の材木としての利用価値は高く「松は寸より棟梁の機あり」と言われれるほどで、粘りがあり丈夫な事から梁をはじめ建築材に多く使われてきました。</div><div>また、地中や水中でも腐りにくいマツ材は土木工事において古くから杭として使われてきました。</div><div>それ以外にもマツは燃料としても火力が強く、かつては薪として製塩や鍛冶屋の仕事に使われ、マツの葉は薪の焚き付けとして利用されていました。 現在でも長時間高温を必要とする備前焼などの焼き物にはマツの薪が使われています。</div><div><br></div><div>このようにマツが材木としてだけでなく燃料として優れている事、かつては普段の生活でも利用されていたものの、今では利用されなくなった事が松原の衰退に大きく関わっているようです。</div><div>というのも、戦時中、燃料不足に陥った際、マツの根から採れる松根油で飛行機を飛ばす計画が持ち上がり、かなりのマツが切り倒されたといいます。また人による松葉の利用もなくなると松原には落ち葉が積もるようになり、自然発芽による幼木の成長は阻害され、土壌の養分が豊富になりやせ地でなくなるにつれマツの樹勢は衰えていきました。</div><div>そこに外来性で免疫を持たないマツノザイセンチュウによる被害も重なるなどして、現在では懸命な保護活動により松原の状態を維持しているのが現状のようです。その活動で大きな意味を持つのが落ち葉かきで、これは今では絶滅危惧種に加えられたマツタケの収穫においても必要不可欠な作業となっているそうです。</div><div><br></div><div>最後に庭木としてのマツの利用についてふれると、ここでもまた時代の変化によりニーズは減る一方で、買い手がつかない事から庭木としての生産も減っているといいます。それは樹木管理する機会の減少にもつながり、どちらの現場にとっても技術や文化の伝承が課題ともいえそうです。</div><div><div><br></div><div><br></div><div>○アカマツの手入れ</div><div> </div><div> 剪定 11~2月 及び 5~7月</div><div><br></div><div> みどり摘み(新芽が柔らかいうちに摘み取る作業) 5月中旬から6月上旬</div><div><br></div><div> 移植、植栽 2、3月 及び 5、6月</div> <br></div><div><br></div><div><br></div>
-

- ナツツバキ(夏椿)
- <strong>ナツツバキ(夏椿)</strong><div>○ツバキ科ナツツバキ属 / 落葉高木 / 雌雄同株 / 日なた~半日陰</div><div><br></div><div>夏の始まりに椿に似た花を咲かせることからこの名がある。別名を沙羅の木(シャラノキ)というが、これは沙羅双樹からきている。「祇園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり 沙羅双樹の花の色 盛者必衰の理をあらはす」平家物語の冒頭に登場するこの沙羅双樹はお釈迦様が入滅の際に時ならぬ花を咲かせたという伝説があり、仏教においては悟りを開いた時の菩提樹と生まれた時の無憂樹とともに三聖木のひとつに数えられている。</div><div><br></div><div>本来はインド原産のフタバガキ科の常緑高木のサラソウジュをさすが、日本の気候では育たないため日本での沙羅双樹にはナツツバキが当てられたか、間違えた認識がそのまま定着したとされている。日本の寺院にナツツバキの植栽があるのはこのためで、菩提樹も同じ理由でクワ科のインドボダイジュの代わりにシナノキ科のボダイジュが植えられている。</div><div><br></div><div>6月から7月頃に咲く白く清楚な花が椿に似るのは見た目だけではなく、散ることなく落ちるのも同じである。一日花であるナツツバキの花は朝に咲いて夕方には散ることなく落ちてしまう儚さがあり、樹上に咲いているときは葉に隠れて見えにくいため、落ちて初めて花の時を知らせるというのもまた風情で、花鳥風月の対象として盛んに詠まれ、夏椿、沙羅の木、沙羅双樹は盛夏の季語でもある。</div><div><br></div><div>庭木としても人気でよく植えられるものの、植える時には場所や土壌状況には注意が必要となる。冷温帯の山林内に生育するナツツバキは日あたりを必要とするものの乾燥や直射日光を嫌い肥沃な土壌を好むため、場所を見極め土壌条件を整える必要があり、西日には特に注意が必要となる。</div><div><br></div><div>自生する山林では他の木と混じって生育しており群生をつくる事はほとんどないとされているものの、兵庫県の有馬富士公園とささやまの森公園には群生が見られ天然記念物となっている。分布地では岩手県の大船渡市が北限とされ、本州の南西部の山地に広く分布し、四国、九州の鹿児島まで自生し、朝鮮半島の南部にも自生する。</div><div><br></div><div>○ナツツバキの手入れ</div><div><br></div><div> 剪定 9月~10月 及び 2月~3月</div><div><br></div><div> 移植、植栽 2月~3月 及び 5月~6月</div><div><br></div>
-

- タイサンボク
- <strong>タイサンボク</strong><div>○モクレン科モクレン属 / 常緑高木 / 雌雄同株 / 日当たりを好むが日陰にも耐える</div><div><br></div><div>タイサンボクは明治の初め頃に渡来した北アメリカ原産の樹木で、別名を白蓮木(ハクレンボク)とも呼ばれます。また、葉の裏の色から紅背木と呼ばれる事もあったようです。この葉裏の色は褐色の毛が密集していることによります。</div><div>葉も大きく厚い革質ことも相まって鬱蒼とした樹姿ですが、それとは対照的に大きく真っ白な花はその清々しさをまずは芳香で梅雨空のもと、私たちに知らせてくれます。</div><div><br></div><div>タイサンボクの漢字は大山木、泰山木と書かれる事が多いですが、牧野富太郎によると花の容姿が大きな盞(さかずき)に似る事から大盞木が正しいとあります。詩的で愛情あふれる観察眼ですね。</div><div><br></div><div>庭木としての人気も高く、下積み時代にお世話になったいくつかのお屋敷にもやはりタイサンボクの大木がありました。</div><div>そして大抵 "大きくなりすぎたから小さくして” と言われるのが常でした。萌芽力の衰えてる老木に無理を強いるのに気が引けたのを覚えています。</div><div><br></div><div>大木になるのでお庭に植えるにはそれなりのスペースが必要ですが、最近主流のリトルジェムという品種は成長が穏やかで大きくなりすぎず、若いうちから花をつけてくれます。そして花の後の実は鳥の好物でもあります。</div><div><br></div><div>○タイサンボクの手入れ</div><div><br></div><div> 剪定 6月~7月 、10月~11月 及び 2月~3月</div><div><br></div><div> 植栽、移植 5月~6月 及び 3月~4月</div><div><br></div>
-

- ケヤキ(欅)
- <strong>ケヤキ(欅)</strong><div>〇ニレ科ケヤキ属 / 落葉高木 / 雌雄同株 / 日当たりを好む</div><div><br></div><div>ケヤキは日本の落葉樹を代表する樹木として、いたるところで目にします。山や川岸に自生するものから都市部の街路樹や公園、学校や社寺に植栽されたものや屋敷林として個人のお庭にあるものまで、広く私たちの身近で四季の移ろいを感じさせてくれます。</div><div>個人的には公園の広場など開けた平地で伸び伸びと扇状に枝を広げ、開放感と安心感を同時に与えてくれる雄大なケヤキの姿がケヤキらしさとして一番に脳裏に浮かびます。そしてもう一つ個人的な印象としては、ケヤキは落葉樹の中でもモミジやイチョウなどの秋を象徴する樹木とは違って冬を象徴する樹のように思います。秋も深まりケヤキの葉が舞い始めるとやがて冬が始まり、夏の間は葉を茂らし日陰を与えてくれた枝がついには裸になり、その枝の間からは冬の日の光が差し込み寒い冬に陽だまりを与えてくれる。大きな木だからこそ、そんな季節の移り変わりと有難味を強く実感させてくれるのだと思います。</div><div><br></div><div>このようなケヤキの大きさや美しさは古くから人々の心に留まり続けてきたようで、日本書紀には飛鳥寺ともいわれた法興寺にあったケヤキの大木についての記述があり、その記述にはその木の下で中大兄皇子と中臣鎌足が打毬をとおして親しくなった事や、いついつに枝が折れたなどの記述がみられるそうです。</div><div>そしてケヤキという呼び名の歴史をみてもその事が表れており、「ケヤキ」は優れた木を意味する「けやき木」からきています。その前には材木としての強さから「槻(ツキ)」とも呼ばれ、古代文学では生命力の強いもの、優れた木、美しい木などの名称の頭に漢字をあてて誉め称えたそうですが、そこでもケヤキは「斎(ユツ)」という美称で詠まれていたそうです。</div><div><br></div><div>現在、日本で一番大きいケヤキは山形県東根市の大ケヤキで高さが28m、幹周りが12.6m、樹齢は1500年以上とされ、天然記念物に指定されています。このほかにも大木として天然記念物に指定されているケヤキは日本全国にありますが、唯一並木として天然記念物に指定されているのが東京都府中市の馬場大門のケヤキ並木です。大國神社の参道でもあるこの道には約150本のケヤキが約500m続いています。また、同じく参道でケヤキ並木が街と美しく調和しているとして名高いのが東京の表参道です。こちらは明治神宮の参道で、ともに参道だからこそ必要な面積が確保され並木の美しさが保たれてきたと言えそうです。街路樹は美観だけでなく防災効果としても重要な存在ですがその維持管理は大きな課題でもあります。街路樹の価値や継続性について正しい知見と深い理解と高い関心をもとに立場を超えた議論や取り組みが望まれます。そして維持管理には剪定は不可欠ですが、ケヤキは太い枝や幹の途中で切り落とすと枝ぶりが損なわれるだけでなく葉っぱの性質まで変化して自然に伸ばした枝に着ける葉より大きくなる特徴があります。そうすると美観が損なわれるため、街路樹など面積の限られた場所では、あまり枝を広げず箒状に枝を伸ばすように品種改良された「むさしの1号」が植えられるケースも増えているようです。</div><div><br></div><div>先にも述べましたがケヤキは材木としての価値も高く、木目が緻密で狂いが少なく耐久年数も長く800~1000年ともいわれています。そのため寺院の建築材としての利用も多く、なかでも有名なのが清水寺の舞台の柱です。ここには高さ12mにも及ぶケヤキの柱が18本使われています。現在の舞台は1633年に再建されたもとありますので390年が経過している事になります。その長い間、部分的な補修のみで保たれているそうです。</div><div>またケヤキの材木としての価値は木目の美しさにもあり、建物の躯体としてでなく装飾用にも用いられ、特に幹にできる瘤の部分の木目は杢と呼ばれ珍重されています。そのほかお盆、家具、楽器、彫刻材などの用途があり、なかでも和太鼓の材料では最高級品とされています。</div><div><br></div><div>〇ケヤキの手入れ</div><div><br></div><div> 剪定 5月~7月上旬 及び 11月~3月</div><div><br></div><div> 植栽、移植 9月~11月 及び 1月、2月</div><div><br></div><div><br></div>
-

- イヌマキ(犬槇)
- <strong>イヌマキ(犬槇)</strong><div>〇マキ科マキ属 / 常緑高木 / 雌雄別株 / 日陰によく耐える</div><div><br></div><div>イヌマキはマキ科マキ属の樹木です。マキ科マキ属に属する樹木は日本ではイヌマキの他にナギが自生し、その二種から成ります。同じマキの名がつくコウヤマキは、その一種から成るコウヤマキ科コウヤマキ属の樹木です。元はスギ科に属していたのが葉の形態の違いなどから独立の科となったそうで、こちらは日本の固有種になります。</div><div><br></div><div>庭木ではイヌマキの変種であるラカンマキがよく使われ、イヌマキに比べ葉の小さいのが特徴ですが区別が難しいほどよく似ており、一般に庭木でマキというとこのどちらかを指しコウヤマキの場合はマキと呼ばずコウヤマキと呼びます。このコウヤマキ、ヒマラヤスギとナンヨウスギと並び世界三大庭園樹と呼ばれるほどの樹木ですが見かける頻度としては日本庭園の歴史で江戸五木(マツ、マキ、カヤ、モッコク、イトヒバ)にかぞえられたイヌマキやラカンマキの方が多いといえます。</div><div>どちらも耐陰性が強く、特にイヌマキ、ラカンマキは加えて海岸近くの山地に生育する事から塩害にも強く、海岸沿いの畑や住宅の生垣として利用されたり、萌芽力が強く枝の誘引もしやすいため玉散らしなどの仕立物として利用されてきました。対してコウヤマキは自然樹形に近い円錐や円柱形で単僕で植えられたり列植されたりしています。</div><div><br></div><div>ところで犬槇(イヌマキ)はなぜ名前の槇(マキ)の前に犬(イヌ)がつくのでしょうか?</div><div>樹木の名前でイヌがつくのは‟劣る”という意味合いで用いられます。実は槇は杉に比べ材木として劣るため、犬槇と呼ばれるようになったそうです。とはいえ槇は杉、檜、樟と共に我が国における樹木の誕生の四種の一つとして日本書紀に登場するほど歴史は深く、その時代から耐朽性の強さの認識があったようで、棺の材木として使用するように書かれており、杉と樟は船の材木、檜は宮の材木として利用法が定められています。ここでの槇がイヌマキなのかコウヤマキなのかははっきりしないようですが古墳からはコウヤマキの棺が出土しているそうです。</div><div><br></div><div>〇イヌマキの手入れ</div><div><br></div><div> 剪定 5月~9月</div><div><br></div><div> 植栽、移植 3月~6月</div><div><strong></strong><div><strong><br></strong></div> </div>