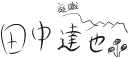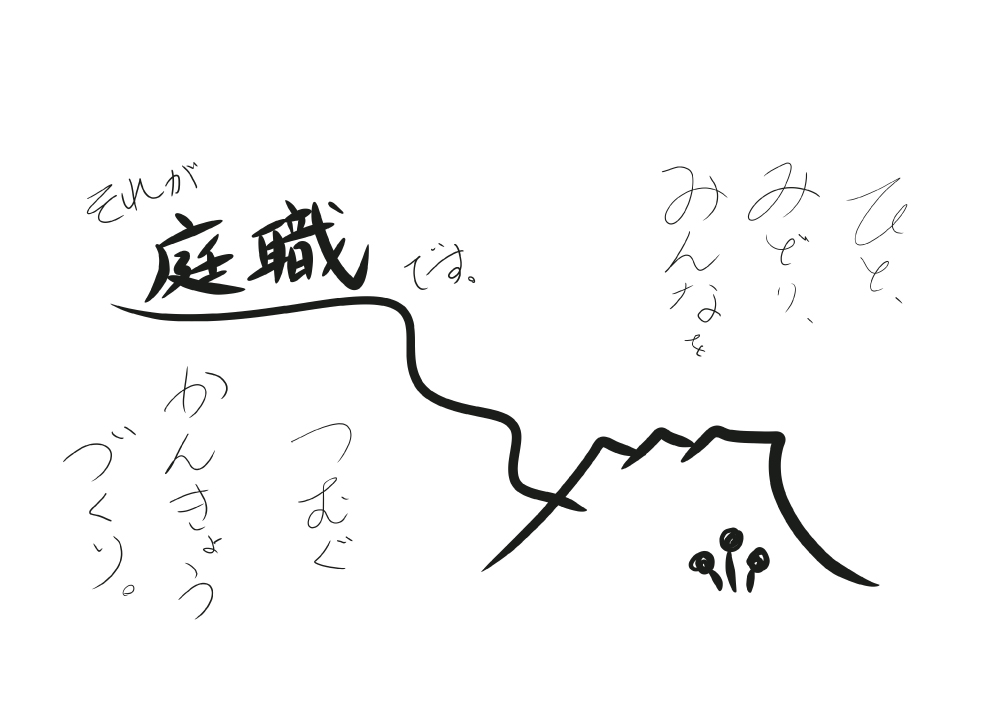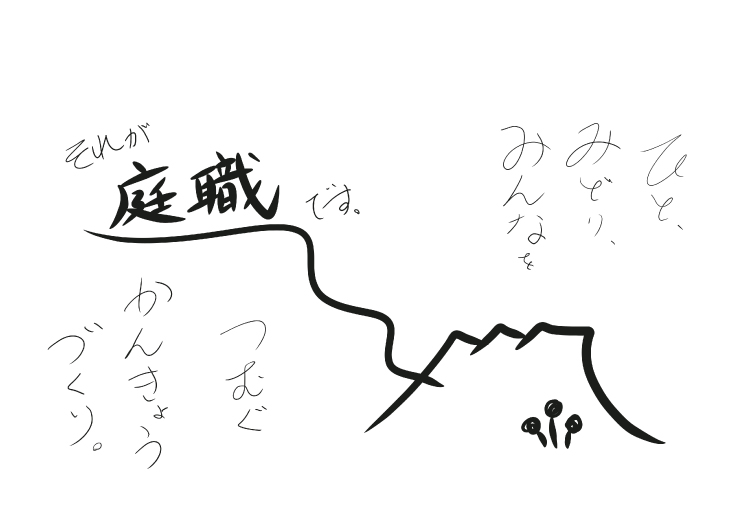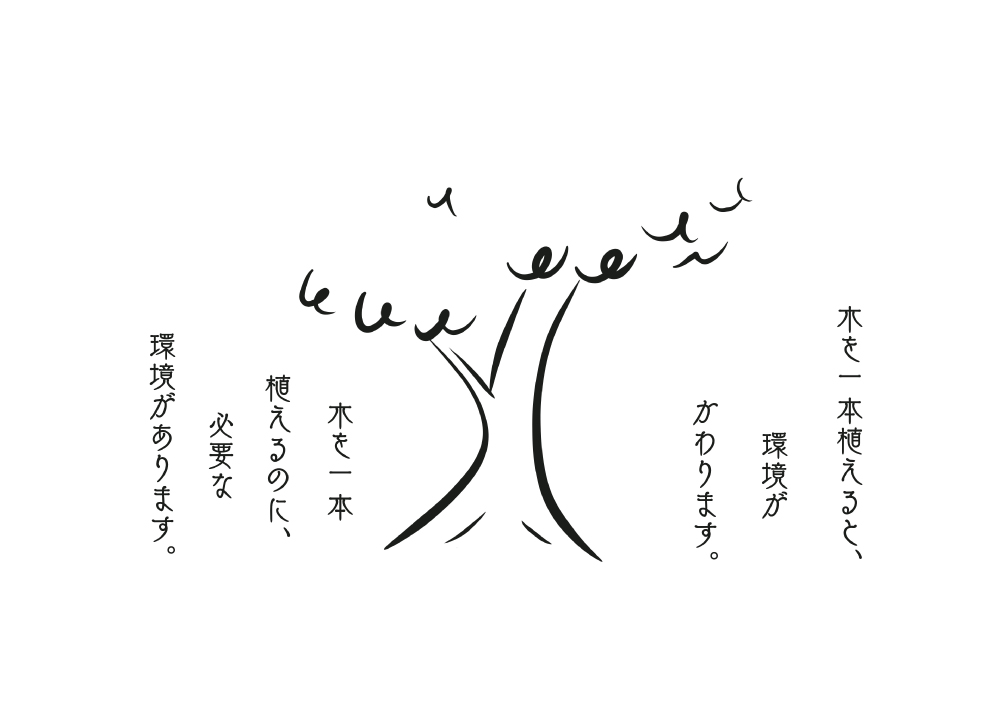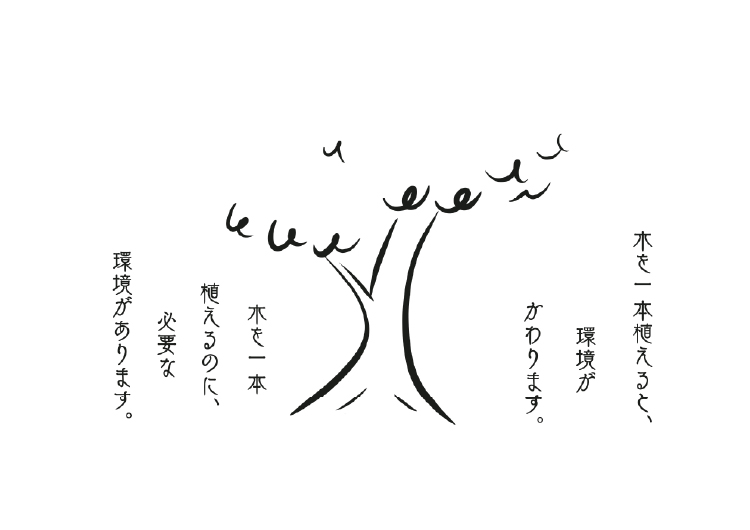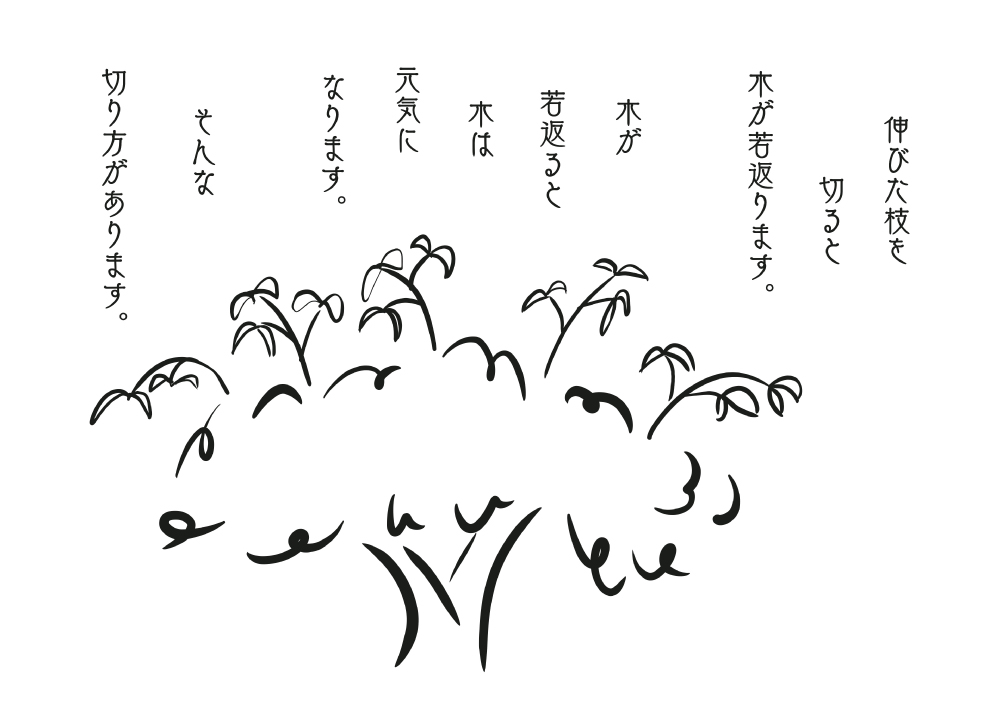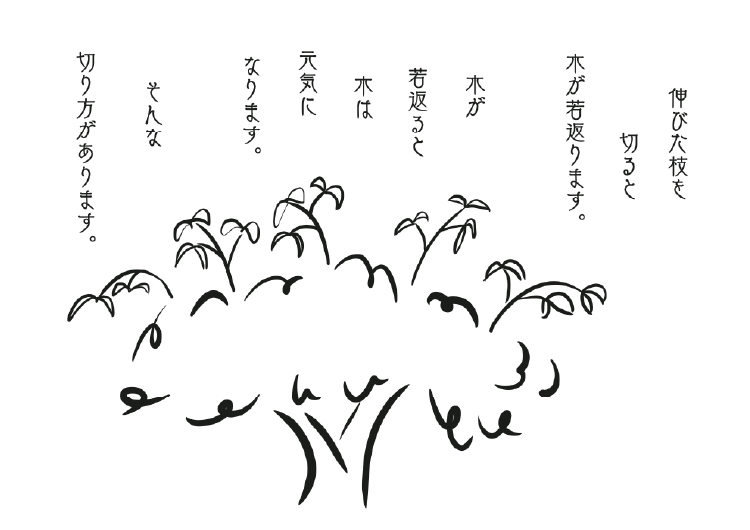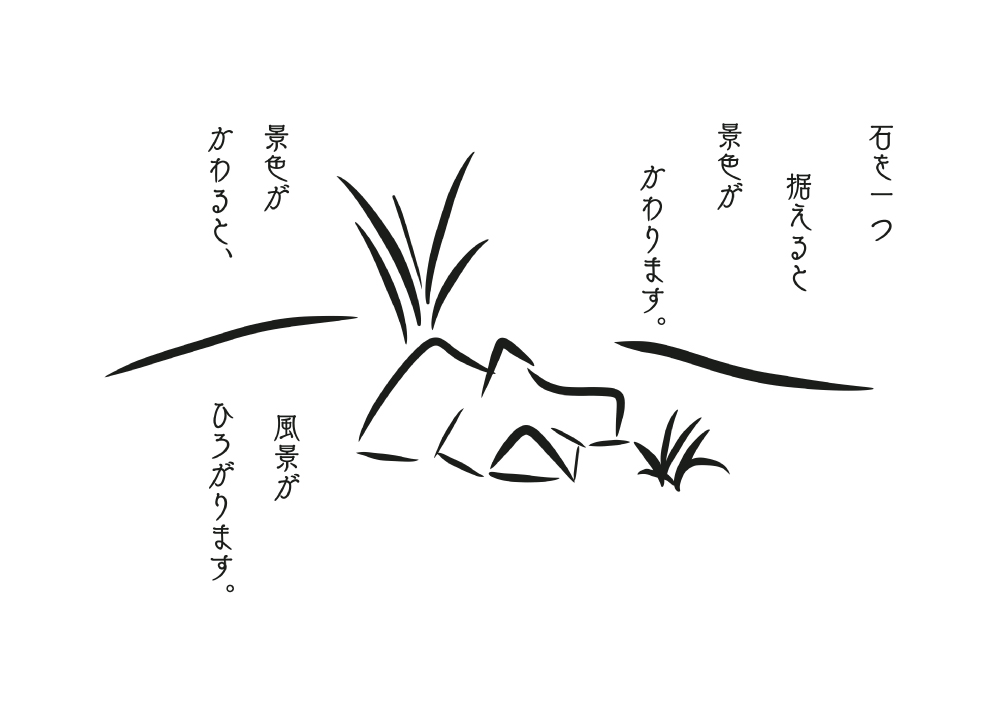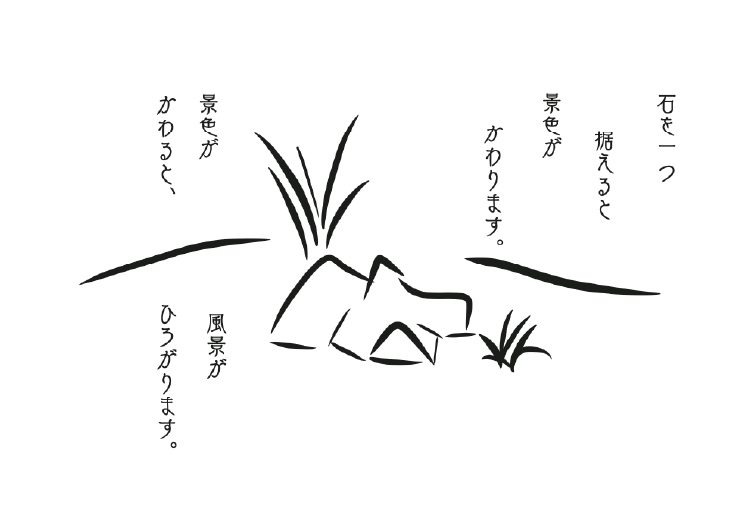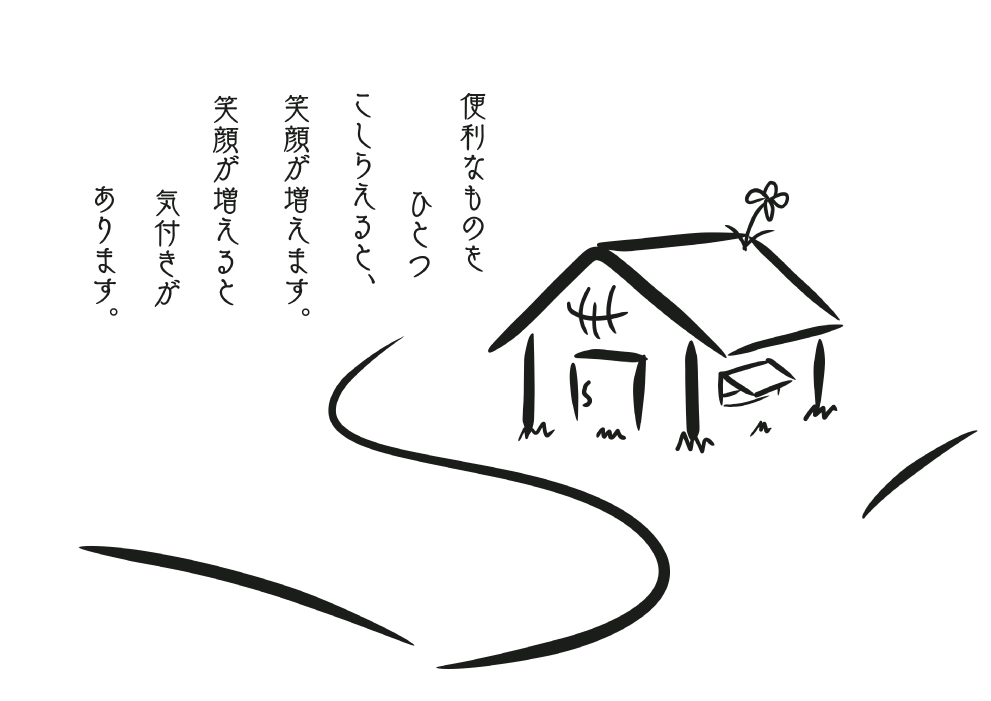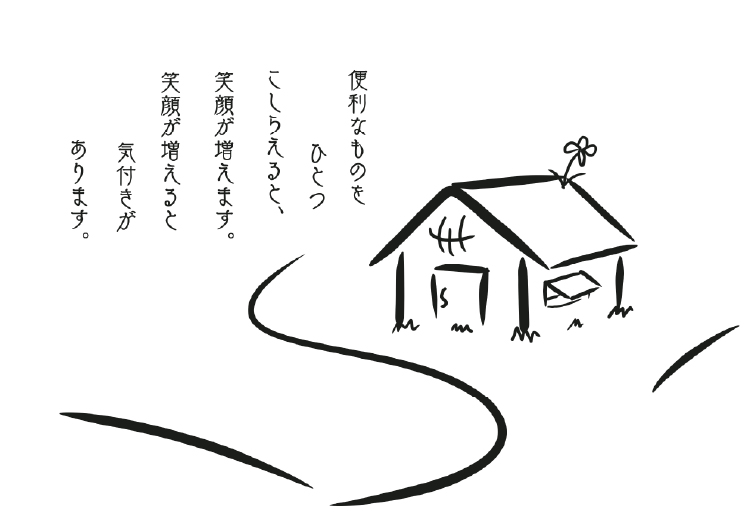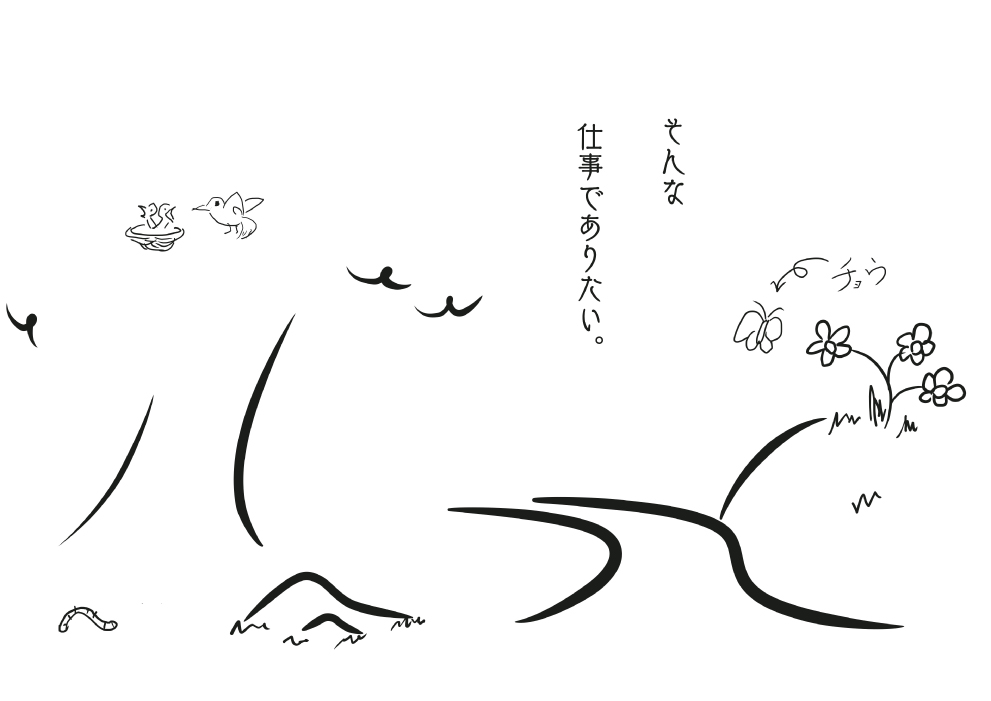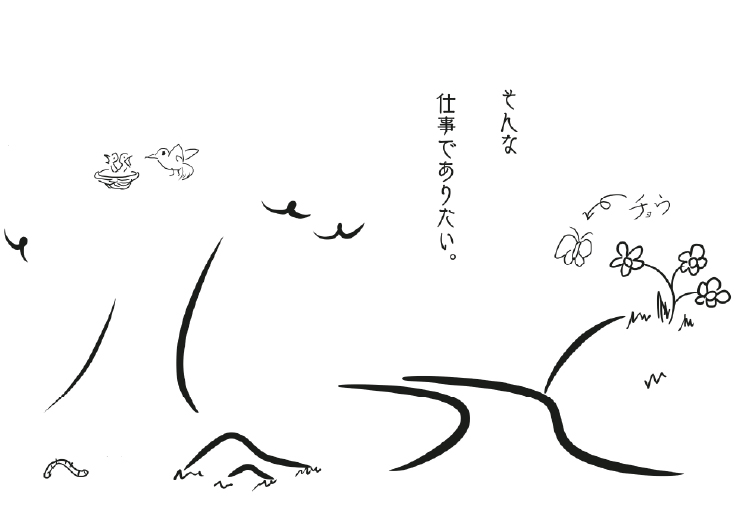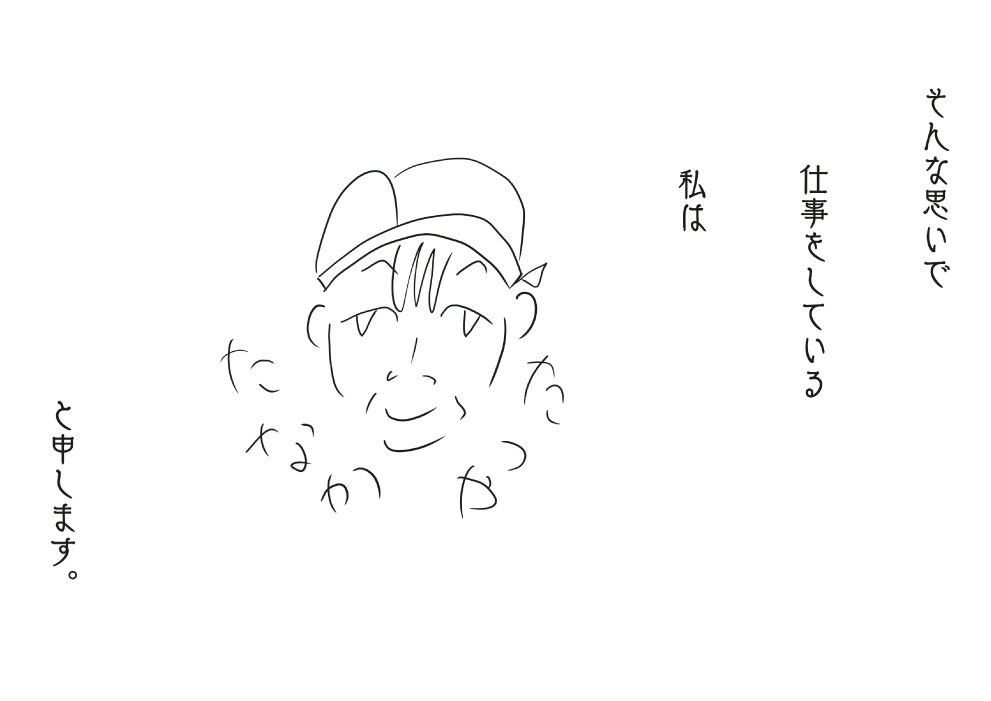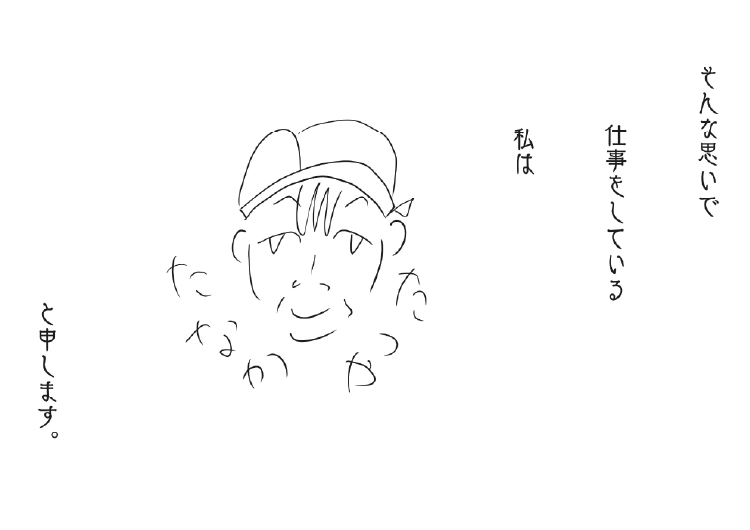スダジイ
スダジイ
〇ブナ科シイ属 / 常緑高木 / 雌雄同株 / 日当たりのよい所を好む
照葉樹林を形成する代表的な樹木のひとつで神社の境内や鎮守の森でもよく見かけるスダジイは、一般的にはシイノキと呼ばれ庭木や公園樹木としてもよく見かける。若葉の頃に黄金色の花序で樹冠を飾り独特の芳香を放ち虫を誘う、人にとってはいい香りというよりはむせるような香りである。実りの秋にはたくさんのどんぐりがなり森の生き物の貴重な食料となる。人にとっては自然工作の材料としての方が馴染み深いが、スダジイのどんぐりはカシやコナラなどの他の種のような渋みはなく、甘みがあり食べられる。
スダジイの近縁種にはコジイがあり、別名ツブラジイとも呼ばれ、二種の見分けは難しい。大きな違いとしてはスダジイの幹では縦に割れ目ができるがコジイは平滑で割れ目ができない事や、スダジイのどんぐりが長楕円形なのに対しコジイのは球形になるという違いがあるほか、環境と分布地の違いではコジイは乾燥地を好み、スダジイは海沿いや河川流域、山地の斜面地などの空中湿度の高い土地を好む。スダジイの分布は福島県以南で日本海側にも新潟県佐渡島を北限に分布があるがコジイは関東以西の内陸部を中心とし日本海側にはほとんど分布がない。
また、スダジイは長寿の樹木で照葉樹林を形成するのに対しコジイは腐朽菌が入って枯死しやすいため照葉樹林ではスダジイにとってかわられる。照葉樹林とは極相林ともいい、いわば森の完成形で、言い換えれば人の手が加えられていない森という事なので、そういう森は全国的にもほとんど残っておらず、スダジイの大木も数は少ないとされてきたが近年、伊豆諸島にはスダジイの大木が比較的多く残っているらしい。
シイ類に入りやすい腐朽菌はシイサルノコシカケで公園樹木や庭木でも度々目にするが、シイサルノコシカケがあるからといって即座に伐採が必要かといえばそうではなく、枯れたり倒木の危険があるかの判断は慎重に行う必要がある。
また、庭木でシイサルノコシカケに侵されるのには剪定が多少なりとも影響している場合がある。というのも関東では以前まで敷地の境界にシイノキを植えていたという。以前に比べ越境枝に神経を使う近年の住宅事情ではその事でかえって強剪定の対象になりやすいからだ。
スダジイの大木が少ない理由には木材としてあまり有用ではないという事も影響している。木材として使われなかったため、植林もされず森林開拓で減るばかりだった。木材以外の利用用途としては、シイタケの原木や樹皮を乾燥させて染料として使われてきた。
〇スダジイの手入れ
剪定 2~6月 及び 9月~11月
移植、植栽 2月~3月 及び 5月~6月